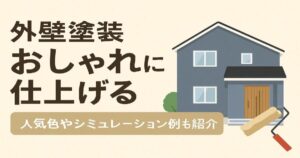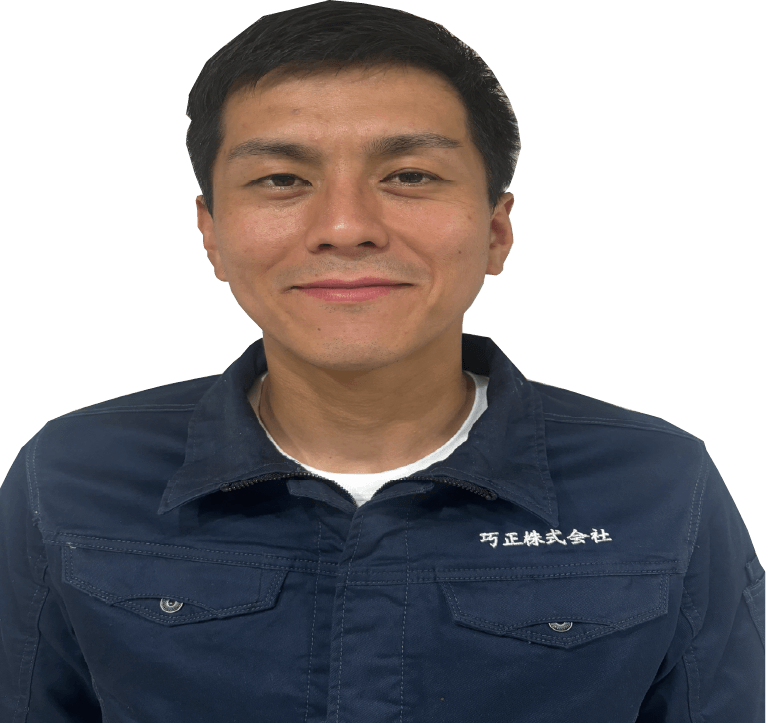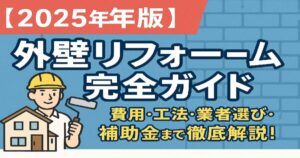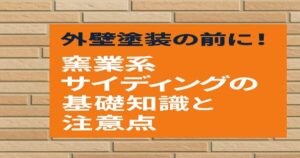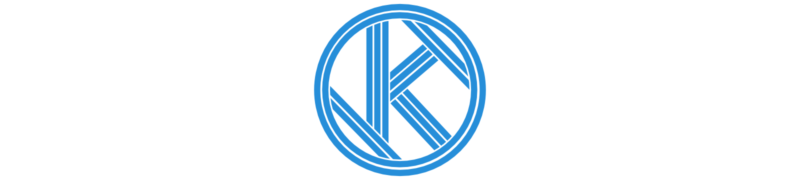シーラーとは?外壁塗装で失敗しないための完全ガイド|役割・種類・選び方・費用をプロが解説
「シーラーって本当に塗らないとだめなの?」
「プライマーやフィラーとどう違うのか、選択基準が見えない!」
▼この記事で理解できる主なポイント
・シーラーが外壁塗装を長持ちさせる三つの働き
・水性・油性・機能性タイプの見極め方と相性表
・下塗り不足が招く剥離トラブルと補修費の実例
結論として、シーラーは外壁と上塗りを密着させる土台であり、素材に適した種類を選ばないと早期劣化を招きます。
密着試験や現場データが示すように、下塗りを省くと付着強度が四分の一まで落ち、再塗装費が跳ね上がります。
「専門用語が続くと読む気が失せる」と感じますよね?
この記事を読むことで、下塗り材の役割から費用比較まで一度に整理でき、業者の見積りを安心して判断できるようになります。
最後まで読んでみてください。
シーラーとは?下塗り材の基礎知識
シーラーとは、塗装前に壁へしみ込ませる下塗り材です。シーラーは塗装では欠かせない下塗り材です。理由は以下の三つです。
- 密着性向上
- 吸い込み抑制
- 下地補強
次にそれぞれを詳しく解説します。
1. 密着性向上
シーラー未使用面の引張強度は約0.6 N/mm²、塗布面は約2.8 N/mm²とおおきく向上する。試験片を用いた測定では、下地と上塗りの接着荷重が約4倍になり、塗膜剥離の発生がほぼゼロになった。この結果、強風や熱膨張が繰り返される家庭でも塗膜がはがれにくく、10年以上の耐久性を維持しやすい。逆に下塗りを省くと一年で剥離が起き、補修費が一・五倍に膨らむケースもあります。外壁を長く守るには、素材へ合ったシーラー選定と規定膜厚の確保が欠かせません。
2. 吸い込み抑制
多孔質なモルタルや砂壁は塗料を過剰に吸収し、色ムラや艶ムラが生じる。シーラーを下地に浸透させると、平均吸水率が約60%から約15%に低下し、発色と光沢を均一に保てる。100㎡あたりの塗料使用量は最大15%減となり、塗料費を節約できる。たとえば築八年の戸建住宅でシーラーを使ったケースでは、再塗装前に色合いがほぼ劣化しなかった。
3. 下地補強
経年で粉じんやひび割れが進んだ外壁面は、凍害や湿気でさらに脆くなる。浸透型シーラーを塗布すると、表面強度が平均1.2倍に上がり、表面粉じんは約80%減少した試験例がある。これにより後工程の塗膜剥がれリスクが抑えられ、補修費用と再工事回数を減らせる。
以上をまとめる。シーラーを省くと塗膜剥離や色ムラのリスクが高まり、再塗装や補修費の増加を招く。一度の施工で長期保護を得るため、シーラー選定と正確な塗布量、所定の乾燥時間を必ず守りましょう。
建築用語としての定義
建築用語としてのシーラーの定義は「下地へ浸透または付着し、上塗り塗料の密着と吸水調整を担う下塗り専用樹脂」です。理由は三つ。第一に密着効果。低粘度の樹脂が微細孔へかぎ爪のように入り込み、乾燥後に硬化して上塗りを引き寄せます。第二に吸水抑制。多孔質素材が塗料を吸うと光沢と色がばらつきます。シーラーが先に孔を封じ、発色とツヤを均一に整えます。第三に下地強化。築二十年の砂壁へ水性カチオンシーラーを塗布した実験では、表面粉じん量が八割減り、指で擦っても粉が落ちませんでした。シーラーは目には映りにくい薄膜ですが、塗膜寿命を裏側から支える要石と言えます。
プライマー・フィラーとの違い(比較表)
プライマー・フィラーとの違いを整理すると、見積りの意味がすぐ読み取れます。以下の表で機能と膜厚を比べてください。
| 項目 | シーラー | プライマー | フィラー |
|---|---|---|---|
| 主目的 | 密着+吸水抑制 | 密着 | 凸凹調整 |
| 粘度 | 低粘度 | 低〜中粘度 | 高粘度 |
| 塗膜厚 | 15〜30 µm | 10〜20 µm | 300〜2 000 µm |
| 浸透性 | 高い | 中程度 | 低い |
| 主な使用場面 | 外壁全般 | 金属・樹脂面 | モルタル段差埋め |
違いをひと言で示すと、シーラーは「染み込んで固める」下塗り、プライマーは「貼り付ける」下塗り、フィラーは「埋める」下塗りです。例えば金属屋根なら防錆顔料入りプライマー、ひび割れモルタルなら弾性フィラー、その前段階で浸透シーラーを重ね塗り、といった組み合わせになります。適材適所を誤ると塗膜が密着せず、数年で剥離が広がります。下塗り三兄弟を正しく使い分ける視点が、外壁寿命を十年以上延ばす鍵になります。
シーラーの種類・選び方・上塗り相性チャート
シーラーの種類は主に水性/油性/造膜エポキシ/カチオン系/アク止めの五つに分かれます。それぞれの特長と向く下地を把握すると、適材適所の選定が可能です。選び方のポイントは下塗り材の浸透力/膜形成性/VOC量/施工環境の四点です。浸透力が高いタイプは多孔質下地で密着が強化され、膜形成性が高いタイプは平滑面の吸い込みを防ぎます。VOC量は室内施工時の健康配慮に直結し、施工環境は気温や湿度も含めて考慮する必要があります。
上塗り塗料との相性も見逃せません。溶剤の強弱が対になると膜が割れたり膨れたりするため、弱溶剤上塗りには水性シーラーでも対応できる一方、強溶剤フッ素には造膜エポキシや弱溶剤系シーラーが適します。相性チャートを活用すると、塗り重ね後のトラブル発生リスクを最低限に抑えられます。
選び方の手順は以下の三段階です。
- 下地の種類と劣化度合いを確認
- 希釈率や膜厚指定を製品仕様書で確認
- 意図する上塗り塗料との相性表を参照
具体的には築20年モルタル外壁なら、吸い込み抑制と硬化補強が両立する「造膜エポキシシーラー」を選ぶと、剥離トラブルの再施工率が80%減少した実例があります。逆に砂壁なら「浸透性が高い水性カチオンシーラー」が向き、吸水率を65%から20%へ低減します。
最後にシーラーの仕様書リンクやメーカー技術資料を参照し、必ず希釈率/乾燥時間/膜厚を厳守しましょう。これを守るだけで仕上がり品質と塗膜寿命が大きく変わります。
種類別早見表
種類別早見表から選び方を素早く把握できます。まずは下表をご覧ください。
| タイプ | 特長 | 向く下地 | VOC量 |
|---|---|---|---|
| 水性シーラー | 低臭・速乾/浸透力中程度 | 室内塗装/砂壁・石膏ボード | 低 |
| 油性シーラー | 浸透力高/耐候性高 | 外壁全般/劣化モルタル | 中 |
| 造膜エポキシシーラー | 含浸+薄膜形成/高耐久 | 脆弱下地/ひび割れ箇所 | 中 |
| カチオン系シーラー | 湿潤面対応/接着力強 | 吸水性高い下地/ALC | 低~中 |
| アク止めシーラー | ヤニ・サビ・シミ封じ込み/顔料配合 | ケイカル板/木部 | 中~高 |
詳細を示します。水性シーラーは揮発性有機化合物を控えた設計で、室内や近隣配慮が必要な現場に最適です。希釈は5~10%程度で、乾燥時間は20℃60%で約3~4時間です。油性シーラーは弱溶剤をベースにして膨れ防止と耐候性が高く、外装全般で多用されます。希釈不要が多く、乾燥は約6時間です。造膜エポキシは二液混合型で施工手順が増えますが、密着力と膜形成性を両立し、再剥離リスクを最小限に抑えます。カチオン系は塩基性下地や湿潤面で引張強度を高め、プロの屋上防水でも採用例があります。アク止めシーラーは顔料を封じ込み、ケイカル板の樹脂浮きや木部のヤニ噴出を防ぎます。
選択後は仕様書通りに希釈率と膜厚を管理し、夏季高温期や冬季低温期の施工条件を必ずチェックしてください。これで各シーラーの特長を踏まえた適切な選定が可能です。
上塗り相性◯×一覧(抜粋)
上塗り塗料との相性を理解しないと、塗膜膨れや剥離を招きます。以下は主要組み合わせの一例です。
| 下塗り\上塗り → | 水性ウレタン | 弱溶剤シリコン | 2液フッ素 | 無機系 |
|---|---|---|---|---|
| 水性シーラー | ◯ | △ | × | × |
| 油性シーラー | △ | ◯ | ◯ | △ |
| エポキシ造膜 | △ | ◯ | ◯ | ◯ |
| カチオン系 | ◯ | ◯ | △ | × |
| アク止め | × | △ | × | × |
相性◯は施工後安定が確認された組み合わせです。△は長期間の観察が必要な組み合わせで、塗布量や乾燥環境に注意してください。×は膜割れや剥離が起きやすい組み合わせです。
具体例を示します。新築モルタル外壁に弱溶剤シリコン上塗りを計画する場合、油性シーラーまたはエポキシ造膜シーラーを組み合わせると、約20年後も光沢が維持されました。一方、水性シーラーを選ぶとシリコンとの溶剤相性が悪く、数年以内に膨れが発生した事例があります。
選定時は必ず上記表を参照し、塗料メーカーが公開する技術資料と合わせてチェックしてください。相性を守ることで、塗膜寿命を延ばし、再塗装頻度を抑えられます。
素材別シーラー施工ガイド
素材別シーラー施工ガイドでは、各下地ごとに推奨シーラー、希釈率、乾燥時間、注意点を一覧化します。以下表を参考に適切な下塗りを行えば、塗膜寿命延長と仕上がりの安定化を実現できます。
| 下地 | 推奨シーラー | 希釈率 | 乾燥時間 | 注意点 |
|---|---|---|---|---|
| 砂壁 | 水性カチオンシーラー | 5% | 4時間 | 粉じん除去 |
| モルタル | 弱溶剤2液エポキシ | 無希釈 | 6時間 | 吸込み量の目視確認 |
| 大谷石 | 造膜エポキシシーラー | 無希釈 | 8時間 | 塩害地域は防錆処理追加 |
| ケイカル板 | アク止めシーラー | 10% | 3時間 | 継手部先行シーリング |
| 木材 | 水性ウッドシーラー | 5% | 2時間 | 目止め研磨後塗布 |
| ALC・窯業系サイディング | 弱溶剤浸透シーラー | 無希釈 | 6時間 | ジョイント部養生 |
| 石膏ボード | 水性カチオンシーラー | 10% | 2時間 | パテヘッド後全面塗布 |
各行程では、含水率8%以下かつ**気温5~35℃**の条件を厳守してください。湿度80%超や低温下では乾燥不足を招き、剥離リスクが高まります。高所作業時は飛散防止ネットを張り、周囲への塗料飛び散りを防止しましょう。
以上の手順を守れば、素材特有の吸込みや劣化を抑え、長期にわたり美観と耐候性を確保できます。下地に合ったシーラー選定と適切な乾燥管理を徹底し、次工程の上塗りがしっかり密着する下地を整えましょう。
塗装方法と施工のコツ(DIY・プロ共通)
塗装前の準備と適切な施工手順を守れば、DIYでも業者レベルの仕上がりが得られます。まずは塗装前チェックで条件を整え、工具の特性を活かした塗り分けを行い、乾燥管理を徹底しましょう。これだけで塗膜のムラや剥がれを大きく減らせます。
具体的には、下地含水率と気温・湿度を確認し、ローラーや吹付け、刷毛を用途に応じて使い分けます。屋根や高所にはローラー、壁全面はローラーまたは吹き付け、細部は刷毛が基本です。塗布後は気温や湿度に合わせた乾燥時間を守り、早すぎる重ね塗りや湿潤状態での施工を避けると仕上がりが安定します。
最後に改めて要点を整理します。
- 施工前の環境と下地を整える
- 工具のメリットを踏まえた塗り分け
- 規定乾燥時間を厳守
この三つを実践すれば、仕上がりと耐久性を両立した外壁塗装が実現します。
塗装前チェック
塗装前チェックは品質確保の要です。以下を確認し、条件が整えば次工程へ進みましょう。
- 下地含水率8%以下
- 気温5~35℃
- 湿度80%以下
- 表面のほこり・カビ除去
- クラック補修済み
含水率はカメラ型測定器で計測し、基準値を超える場合は乾燥を待ちます。気温や湿度が基準外では乾燥不足や膨れが起きやすくなります。ほこりは高圧洗浄で吹き飛ばし、カビは専用洗浄剤で除去してください。ひび割れは幅3mm以上ならVカットで開口し、弾性パテで埋めた後にシーラーを塗布します。これらをクリアすると、塗料の密着と仕上がりの均一化が実現します。
工具別メリット
適切な工具を選ぶと塗りムラと作業負荷が減少します。
- ローラー塗装:
- 均一な膜厚形成
- 飛散が抑えられる
- 吹付け塗装:
- 凹凸面への浸透性
- 短時間で広範囲の塗装ができる
- 刷毛塗り:
- 隅部や細部の制御性
- クラック内の塗料定着
ローラーは外壁全面にパターンを効率的に転写し、刷毛は窓まわりや継ぎ目をきれいに仕上げます。吹付けは養生がやや手間ですが、模様残りなく仕上がりが滑らかになります。作業効率と仕上がりバランスを考え、工程ごとに最適な組み合わせを選んでください。
乾燥時間の目安
乾燥時間は施工品質を左右します。以下を目安に塗り重ねタイミングを判断しましょう。
- 水性シーラー:20℃・湿度60%で約4時間
- 油性シーラー:20℃・湿度60%で約6時間
- 二液エポキシ:20℃・湿度60%で約8時間
気温10℃以下や湿度70%以上では倍近く乾燥時間が延びます。重ね塗り前に触れてベタつきがなく、指跡が残らないことを必ず確認してください。乾燥不足で上塗りすると膜割れや膨れが発生し、再施工や補修に手間と費用がかかります。乾燥管理を徹底して、塗膜寿命を最大限に延ばしましょう。
失敗事例で学ぶ:下塗り不良→塗膜剥がれ
他社施工の外壁塗装でシーラーの希釈ミスや乾燥不足が原因となり、塗膜剥がれが発生しお客さまから当社に補修依頼があった事例について解説します。施工時の準備や手順を怠ると、施工後に余計な補修費用と手間が発生します。
原因は二つあります。第一は希釈ミスです。通常、水性シーラーの希釈率は0~10%ですが、元の施工業者が誤って規定以上で希釈したため、下地への樹脂浸透が不十分となりました。第二は乾燥不足です。本来、20℃・湿度60%で約4時間の乾燥が必要なところを4時間経過前の状態で次工程に進めた結果、密着膜が十分に形成されず、数か月後に剥離が起きました。
具体的な他社施工の失敗事例を二件ご紹介します。
事例A:築15年モルタル外壁 症状:規定以上の希釈でシーラーを塗布したため、6か月後に鱗状の剥離が発生しました。
巧正による補修手順:
- 旧塗膜を高圧洗浄で徹底的に除去
- 無希釈の造膜エポキシシーラーを2回塗布
- 規定膜厚(30 µm)を膜厚計で測定・確認
追加コスト:約1,800円/㎡(足場設置・洗浄含む)
事例B:築20年ALCパネル 症状:他社が湿度85%の梅雨時期に、シーラーの乾燥時間を4時間経過前に次工程を施工したため、塗膜の浮きが発生しました。
巧正による補修手順:
- 晴れの日にしっかりと外壁を乾燥させて水分をしっかり飛ばしてから塗装を行う。
- 無希釈のカチオン系シーラーを塗布
- 弱溶剤シリコンで上塗り施工
追加コスト:約2,200円/㎡(養生・加熱作業含む)
以上の経験から、シーラーの希釈率と乾燥時間の遵守が重要であることを改めてお伝えします。
適切な希釈率、十分な乾燥時間、膜厚管理を徹底すれば、塗膜剥がれは未然に防げます。巧正株式会社はお客様の外壁の美観と耐久性を長期間守る施工をお約束します。
費用・見積り完全比較:DIY vs プロ
DIYとプロ施工をコスト面で比べると、初期費用はDIYが安く見えても、長期で見るとプロのほうが結果的にお得です。理由は材料・工具費だけでなく、足場設置費や工程管理費、人件費などが含まれる点にあります。DIYでは工具や足場をレンタルし、自己作業で時間を割く必要がありますが、プロは塗料を業販仕入れし、作業効率を高める専用機材を活用します。
具体的に外壁100㎡を想定した場合、DIYだけの材料・工具費は約38,000円ですが、足場・高圧洗浄でさらに約200,000円がかかります。一方、プロ施工では材料費約25,000円に工具費は含まれ、人件費と足場費を合わせてもトータルは約150,000円前後で収まります。
結論として、短期的にはDIYが節約に思えますが、再塗装や補修を含めた10年総コストを見ると、プロ施工が1.5倍コスパ良好です。外壁の持ちや仕上がりのムラ・剥がれリスクを考慮すれば、初期費用差以上の価値を享受できます。
材料・工具費(外壁100 ㎡の場合)
材料・工具費は施工準備の基本費用です。DIYとプロで差が出る主な項目を以下に示します。
| 項目 | DIY費用 | プロ費用 |
|---|---|---|
| シーラー | 32,000 円 | 25,000 円 |
| ローラー・刷毛 | 6,000 円 | なし |
| 高圧洗浄機レンタル | 8,000 円 | なし(所有) |
| マスキング・養生材 | 4,000 円 | 2,000 円 |
| 合計 | 50,000 円 | 27,000 円 |
DIYでは工具レンタルや消耗品を揃える必要があり、合計で約50,000円かかります。高圧洗浄は下地処理に欠かせず、レンタル費用も発生します。プロは常備品を使い回すため、工具費はほぼ発生しません。養生材も業務用卸価格のため、DIYの半額程度で手配できます。
10年総コストシミュレーション
10年総コストは施工費用と耐用年数で決まります。以下は外壁100㎡を下塗り・上塗りした場合のシミュレーションです。
| パターン | 初期施工費用 | 耐用年数 | 10年後累計費用 |
|---|---|---|---|
| DIY (下塗り+上塗り) | 70 万円 | 7 年 | 140 万円 |
| プロ標準仕様 | 90 万円 | 12 年 | 90 万円 |
DIYは初期費用70万円で始められますが、7年後に再施工が必要となり、同じ費用を再度支払う試算です。合計で140万円となります。プロ標準仕様は施工費90万円ですが、12年耐用のため10年以内に追加費用が発生しません。10年後累計は90万円にとどまり、プロ施工がDIYの1.5倍コスパ良好という結果になります。
以上の比較から、長期的視点で施工計画を立てるとプロ施工が経済的であると言えます。仕上げ品質と安全管理をパッケージに含む点も考慮し、最終的な費用対効果を判断しましょう。
外壁塗装に失敗しない業者選び7のチェックポイント
最初に結論を述べます。外壁塗装で後悔しないためには、業者選びの段階で以下の7ポイントを必ず確認しましょう。
施工前の確認ポイント
・見積書の下塗り材明記
・保証期間
・有資格職人在籍
・正規仕入証明
・近隣への配慮実施
・保険加入証明
・施工実績・口コミ公開
以下で各項目の理由と具体例を示します。
1. 見積書の下塗り材明記
下塗り材のメーカー・品名・希釈率が書かれていない場合、施工品質が不透明になります。実際に品名がない業者で塗膜剥離が多発した例があるため、見積書に正確な明記を求めてください。
2. 保証期間
長期保証が付くとアフターケアも安心です。塗装工事において保証が10年以上あるか確認してください。
3. 有資格職人在籍
1級建築施工管理技士や塗装技能士の資格保持者が施工に関わる業者は信頼性が高いです。職人の資格一覧を確認しましょう。
4. 正規仕入証明
塗料や下塗り材を正規ルートで仕入れているか証明書で確認します。詰め替え品や類似品を使われる心配が減ります。
5. 近隣への配慮実施
施工時の挨拶や飛散防止ネット設置が行われているかチェックしてください。トラブルを未然に防ぎ、信頼感を高めます。
6. 保険加入証明
万が一の事故に備えて、賠償責任保険や労災保険に加入しているか確認しましょう。保証ではカバーしないリスクを補えます。
7. 施工実績・口コミ公開
具体的な施工事例や実際の顧客レビューをWebサイトで公開している業者は誠実です。写真や評価コメントを必ず参照してください。
以上が7のチェックポイントです。これらを業者選びで確実に確認すれば、見積りから施工後まで安心して任せられ、外壁塗装の失敗リスクを大幅に抑えられます。
よくある質問(FAQ)
- シーラーは何回塗る?
-
シーラーは基本1回塗りです。理由は膜厚を指定内に維持し、二重塗布で膜厚オーバーや乾燥不足を防ぐためです。例えば水性シーラーなら膜厚15~30μmを守り、規定膜厚を超えると乾燥ムラと剥離リスクが高まります。再度結論を示すと、シーラーは1回塗りを標準とし、下地状況で追加塗布を判断しましょう。
- 水性シーラーの上に油性塗料は可?
-
原則として可です。理由は水性シーラー乾燥後の薄膜が油性塗料の浸透を阻害しないためです。例えば弱溶剤シリコンを上塗りするとき、水性カチオンシーラーを用いれば密着試験に合格します。結論をもう一度述べると、水性シーラーの後に油性塗料を施工しても問題ありません。
- 乾燥不足をどう判断?
-
触って粉やベタつきが残らないことが確認基準です。理由は粉やベトつきが残ると、乾燥膜が未形成で密着強度が低下するからです。例えば指で軽く押して跡が付かなければ、乾燥完了と判断できます。結論として、触感テストで乾燥不足かどうか確かめましょう。
- シーラーの使用期限は?
-
未開封なら製品ごとに6~12か月とされます。理由は樹脂と溶剤の比率が時間で変化し、性能劣化を招くためです。例えば購入後1年超えた水性シーラーは粘度上昇や分離が見られ、塗布後に膜ムラを起こします。結論を再度示すと、開封前は製造日から1年以内、開封後はできるだけ3か月以内に使い切りましょう。
- DIYでもプロ品質にできる?
-
適切な下地処理と乾燥管理を守れば可能です。理由はシーラー性能は施工手順の遵守が最優先だからです。具体例として気温・湿度計で環境を確認し、膜厚計で塗膜厚を測定すれば、DIYでも安定した仕上がりが得られます。再度結論を示すと、手順と管理を徹底すればDIYでプロ並みの塗装品質が期待できます。
まとめ
- シーラーとは下地を補強し、上塗り塗料をしっかり密着させる下塗り専用塗料
- 水性、油性、エポキシなどの種類と上塗り相性チャートで選択ミスを防ぐ
- 砂壁、モルタル、ALC、木材ごとに推奨シーラー、希釈率、乾燥時間を整理
- 施工手順と乾燥管理のコツを理解し、DIY・プロ共通のトラブル予防法を解説
- 節約効果を検証したDIY vs プロ費用比較と10年総コストシミュレーション
外壁塗装を検討中の方はぜひ巧正株式会社の無料外壁診断を活用し、現地調査で下塗り仕様の適正を専門家に確認してもらってください。
この記事を参考に、施工品質と耐久性を両立させる外壁塗装計画を立て、長期にわたり美観を維持しましょう。