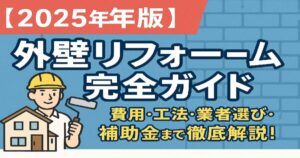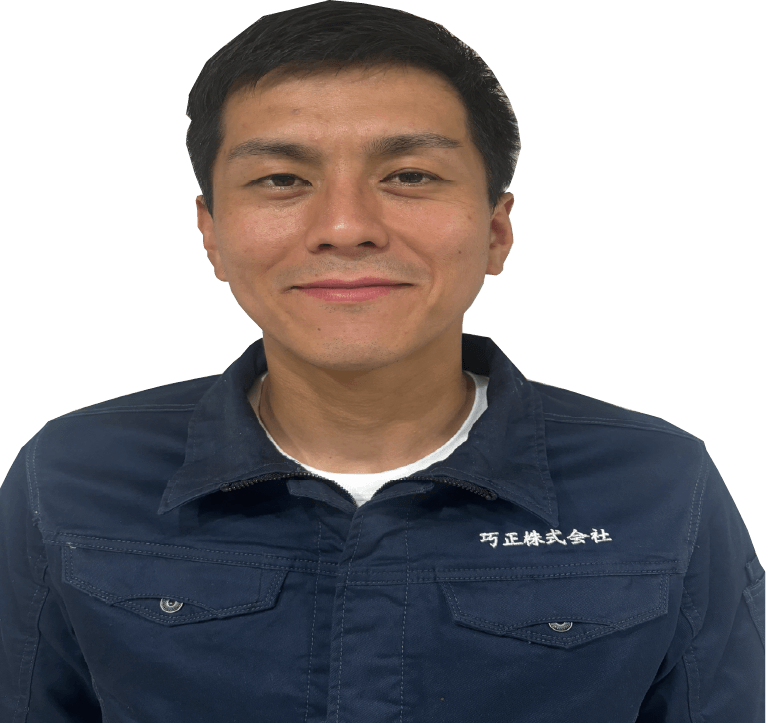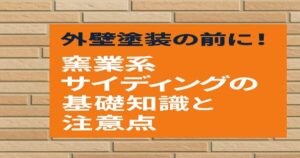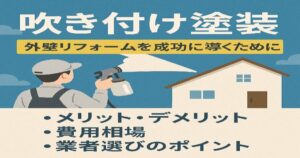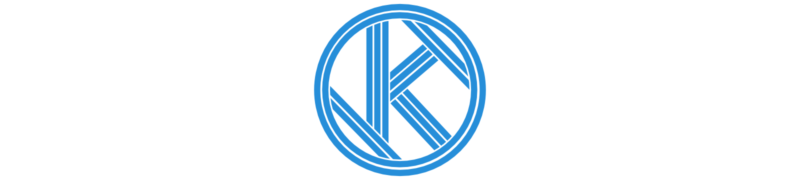シーリングとコーキングの違いが丸わかり!用途・施工・材料・選び方を徹底解説
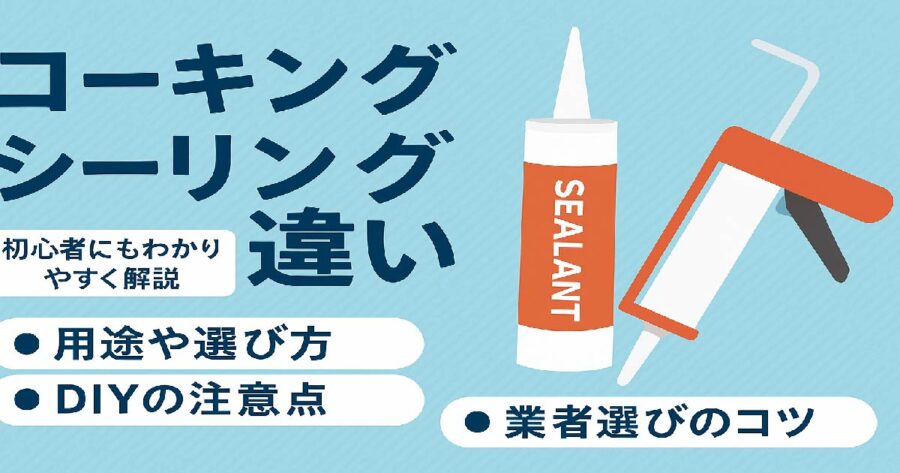
結論:「シーリング」と「コーキング」はほぼ同じ意味で、現場・業界・商品表記の違いで呼び名が分かれているだけです。
重要なのは用語ではなく、材料の種類(変成シリコン等)と工法(打ち替え/増し打ち)を正しく選べているか、です。
「見積書に“シーリング工事”と書いてあるけど、“コーキング”じゃないの?」という疑問はよくあります。この記事では、呼び名の混在理由から、外壁で失敗しない判断ポイントまで分かりやすく整理します。
シーリングとコーキングの違いは?(結論:ほぼ同じ)
作業内容としては、どちらも目地やすき間を充填して防水・気密を確保する工事です。違いは「材料や工法」ではなく、呼び方の慣習にあります。
| 呼び方 | よく使われる場面 |
|---|---|
| シーリング | 建築・外壁塗装・防水工事(見積書/図面/工事名) |
| コーキング | DIY・リフォーム・現場会話(ホームセンターの表記) |
次に大事なのは「外壁の劣化」チェックです
用語の違いより、目地の劣化が外壁塗装のタイミングに来ているかを先に判断すると、足場の二重を避けやすくなります。
呼び名が混在する理由(業界・商品表記・語源)
業界(建築/塗装/DIY)で呼び方が変わる
建築の書面(見積書・図面)では「シーリング」が多く、現場会話やDIY文脈では「コーキング」が多い、というだけです。
ホームセンターの表記が統一されていない
DIY向けは「コーキング材」、成分・性能で語る商品は「シーリング材」と表記されがちです。名称よりも、成分(変成シリコン/シリコン等)と用途を見るのが正解です。
語源の違い(seal / caulk)
英語由来で、seal(密閉)と caulk(すき間を詰める)のニュアンス差がありますが、日本の現場では実質的に同義として扱われます。
どこに使う?使用箇所と役割(外壁・サッシ・水回り)
役割は大きく防水・気密・緩衝(動きに追従)です。とくに外壁は雨水侵入の入口になるため、目地の劣化は要注意です。
- 外壁目地(サイディング等):雨水侵入を止める
- サッシ/換気口まわり:雨仕舞い+気密
- 浴室/キッチン:防水+防カビ
材料の種類と選び方(ここを間違えると失敗する)
「シーリングorコーキング」より重要なのが材料の種類です。外壁でよく使うのは変成シリコン系(塗装可)です。
| 種類 | 特徴 | 向く場所 |
|---|---|---|
| シリコン系 | 防水◎/塗装×(塗料が乗りにくい) | 浴室・キッチン等の水回り |
| 変成シリコン系 | 塗装◎/耐候性◎/外壁で定番 | 外壁目地・サッシ周り |
| ウレタン系 | 密着◎/ただし紫外線に弱め→塗装前提 | 下地補修・塗装前提の目地 |
| アクリル系 | 安価/屋外× | 屋内の非露出部 |
補修方法:打ち替えと増し打ち(選び方)
ここが施主側で一番重要です。古いシーリングが劣化しているなら基本は打ち替えです。
| 工法 | 内容 | 向くケース |
|---|---|---|
| 打ち替え | 既存材を撤去→新規充填 | ひび割れ/剥離/硬化/肉やせがある |
| 増し打ち | 既存材の上に追加充填 | 状態が軽微/サッシ周り等で撤去が難しい |
外壁塗装と同時施工がコスパ◎
シーリング工事と外壁塗装は足場が共通なので、同時施工の方が全体コストが安定しやすいです。
DIYとプロの違い(やってOK/NGの判断)
- DIY向き:浴室など屋内の小範囲/失敗しても致命傷になりにくい箇所
- プロ推奨:外壁目地・サッシ周り・高所(雨漏りリスク+足場/安全が絡む)
見積・業者選びのチェックポイント(ここだけ押さえればOK)
- 材料名(例:変成シリコン系/メーカー・商品名)が書かれている
- 工法(打ち替え/増し打ち)が部位ごとに明確
- 施工範囲(外壁目地○m、サッシ周り○m 等)が書かれている
- 下地処理(プライマー等)が明記されている
- 保証の範囲と年数が説明される
見積の比較で迷ったら、チェックリストも使えます。
よくある質問(FAQ)
シーリングとコーキング、どちらが正しい?
どちらも正しいです。書面・業界では「シーリング」、DIYや現場会話では「コーキング」が多い傾向があります。大切なのは呼び名よりも、材料の種類(変成シリコン等)と工法(打ち替え/増し打ち)が適正かどうかです。
外壁の目地はどの材料を選べばいい?
外壁は基本的に「塗装できる材料」を選ぶのが安全です。一般的には変成シリコン系(塗装可)が定番。浴室用のシリコン(塗装不可)を外壁に使うと、塗料が乗らずに不具合の原因になります。
打ち替えと増し打ちはどう選べばいい?
ひび割れ・剥離・硬化・肉やせがあるなら基本は打ち替えです。サッシ周りなど、撤去が難しい部位は増し打ちが選ばれることもあります。判断基準はシーリング工事ページにまとめています。
まとめ
「シーリング」と「コーキング」は呼び名の違いで、実質は同じ工事です。重要なのは、材料の種類と工法(打ち替え/増し打ち)が適正かどうか。外壁は雨漏りや外壁材の劣化に直結するため、気になる場合は早めの点検が安心です。
写真1枚からOK。外壁目地の状態を見て、外壁塗装のタイミングも含めて分かりやすく整理します。