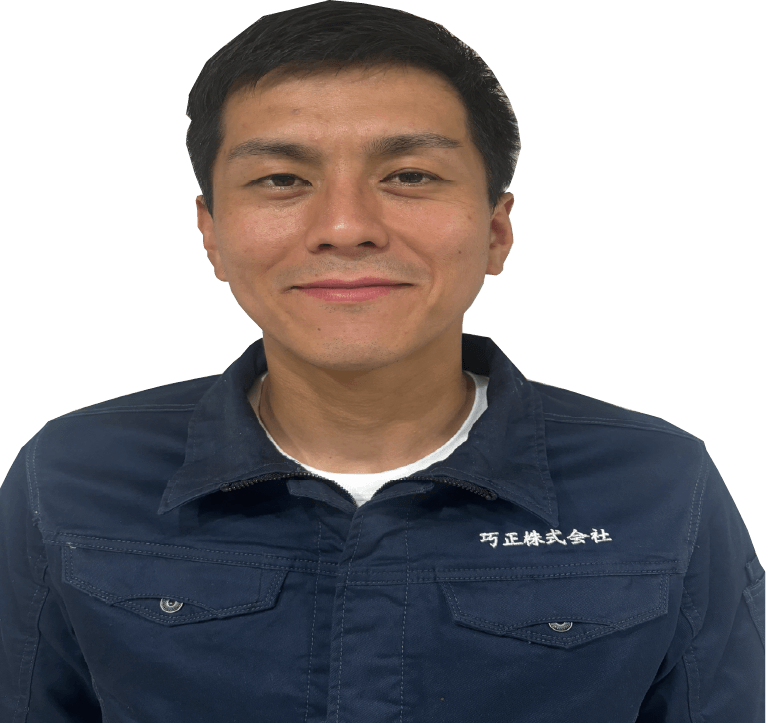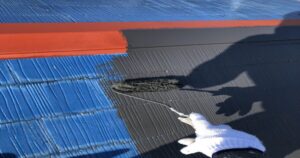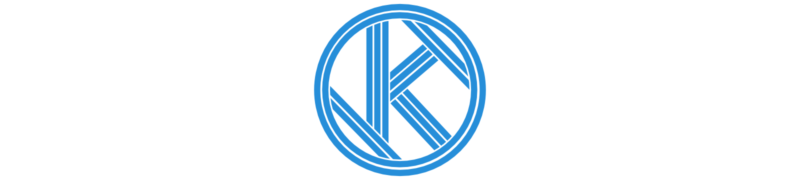八王子市中野山王の鉄部塗装|霧除け板金と換気フードの保護施工
東京都八王子市中野山王にて、霧除け板金(庇)と換気フードを対象とした鉄部塗装工事を行いました。鉄部塗装は外壁塗装と比べて軽視されがちですが、建物の長寿命化と防錆性能の確保において極めて重要な役割を担う工事です。本記事では、一般的な施工レポートにはとどまらず、鉄部が劣化する物理的・化学的要因、地域特性による影響、塗料の材料科学的な視点を織り交ぜながら、八王子市中野山王で実施した施工工程を写真付きで詳しく解説します。
この現場では、外壁塗装を先に行い、それに続く形で付帯部である鉄部塗装を実施しました。鉄部は外壁よりも劣化スピードが速いため、本来は同時施工が望ましい部位です。鉄部に発生したサビは、塗膜の膨れ・剥離を引き起こし、さらに腐食が進むと穴あきや雨漏りにつながります。また、鉄部の劣化は見た目の古さを際立たせるため、外壁がきれいでも建物全体の印象を損ねてしまいます。
今回の記事は、鉄部塗装に焦点を当て、霧除け板金と換気フードに対してどのような施工が行われたのかを、専門的かつ実務者目線で徹底解説します。「なぜケレンが必要なのか?」「錆止めはどう作用するのか?」「八王子市中野山王という地域の気候が鉄部にどう影響するのか?」など、一般的な施工ブログでは触れられない部分まで踏み込んで解説します。
鉄部塗装が建物の耐久性を左右する理由
鉄部は外壁よりも劣化が早い「環境に最も弱い部材」
鉄は外壁材のサイディングやモルタルと比べ、圧倒的に劣化スピードが速い素材です。その最大の理由は、鉄が水と酸素に触れると錆(酸化鉄)が発生するという性質を持つためです。錆の発生は表面で留まらず、内部に向かって進行し、膨張を伴うため、塗膜を内側から押し上げて剥がしてしまいます。塗膜が剥がれた部分からはさらに水が入り込み、腐食が加速する悪循環が発生します。
外壁の塗膜寿命が10〜15年程度であるのに対し、鉄部は5〜7年ほどで劣化が進行することが多く、適切なタイミングでの再塗装を行わないと、塗装では補えず交換が必要なほど腐食が進んでしまうことがあります。特に霧除け板金や換気フードは、雨水が滞留しやすい構造のため劣化が加速しやすく、早期のメンテナンスが欠かせません。
錆の発生メカニズム|化学反応としての腐食現象
鉄部が錆びる要因は「酸素」「水分」「電解質(汚れや空気中のイオン)」です。鉄が水と反応しFe2+(二価鉄イオン)を放出し、それが酸素と結びついて赤錆(Fe2O3・nH2O)となります。この反応は気候条件により左右され、湿度が高く雨水が当たりやすい環境では加速します。
八王子市中野山王は、冬は冷え込みが厳しく、朝晩の気温差も大きいため結露が発生しやすい地域です。この結露が鉄部にとっては大敵で、毎日繰り返される湿気の付着によって錆の進行スピードが加速する環境にあります。
ケレンと錆止めの重要性
鉄部塗装の品質は「ケレンで決まる」と言われるほど、下地処理は重要です。錆を残したまま塗装を行うと、塗膜の内側で錆が進行し、短期間で剥がれを引き起こします。今回の施工では霧除け板金も換気フードも、すべて手工具でのケレンを徹底し、素地調整を行いました。
ケレン後はすぐに錆止め塗装を行います。錆止め塗料は、鉄の表面と空気を遮断することで酸化反応を防ぎ、塗膜の耐久性を大きく高めます。錆止めは“防錆の要”であり、この塗布の精度が寿命を大きく左右します。
霧除け板金(庇)とは|構造と役割、なぜ鉄部の中でも劣化しやすいのか
霧除け板金は、窓や玄関ドアの上に取り付けられた小さな庇(ひさし)で、建物の中でも「雨水・紫外線・風」の3つの影響をもっとも受けやすい部位です。霧除けの主な役割は、窓の上部やサッシ周辺への雨垂れを軽減し、外壁への水の流入や汚れの付着を防ぐことにあります。
一見すると小さな付帯部に見えますが、霧除け板金は金属(主にガルバリウム鋼板・トタン)が使用されており、鉄が本来持つ「酸化しやすい性質」がダイレクトに影響します。雨が当たりやすく、日差しが強く当たる位置にあることから温度変化による膨張収縮が激しく、金属疲労・塗膜の浮き・ジョイント部の劣化が起こりやすいという特徴があります。
また、八王子市中野山王は冬の冷え込みが非常に強く、朝晩の結露が多い地域として知られています。結露水は霧除け板金の裏側にも付着し、外側だけでなく内側でも錆が発生しやすい環境を作り出します。このように、霧除け板金は鉄部の中でも“最もサビが発生しやすい部材”といっても過言ではありません。
霧除け板金の施工工程|ケレンから仕上げまで
① ケレン作業(素地調整)
霧除け板金の塗装で最も重要な工程がケレン作業です。サビ・汚れ・浮いた旧塗膜をヘラ・ワイヤーブラシ・サンドペーパーを使って削り落とし、素地を露出させていきます。ケレンは塗料の密着性を大きく左右する工程であり、どれだけ丁寧に行うかが最終的な塗膜寿命を決めると言われます。
【施工写真:霧除け板金ケレン】

今回のケレン写真では、霧除け板金の表面に付いた細かな酸化物や旧塗膜の浮きを除去している様子が確認できます。金属表面は一見きれいに見えても、実際には目視できないレベルの酸化皮膜や細かな埃が付着しており、そのまま塗装すると数年で剥がれの原因になります。写真のとおり、手工具を使い細部まで丁寧に擦り、素地に微細な傷(アンカー効果)をつけることで、塗膜が強固に密着する状態をつくります。特に端部や角部分は錆が出やすいため念入りに処理を行いました。
② 錆止め塗装
ケレンが完了したら、時間を空けずにすぐ錆止めを塗布します。鉄部は空気に触れただけでも酸化が始まるため、素早い作業が求められます。今回使用したのは「エポキシ系錆止め塗料」で、耐久性と密着性の高さが特徴です。
【施工写真:霧除け板金錆止め】

写真では、霧除け板金の表面に均一に錆止め塗料が塗布されている様子が見られます。錆止めはただ赤色やグレーで塗るだけの作業ではなく、隙間なく塗り広げる高度な技術が求められます。とくに端部・折り返し・ジョイント部分など、水分が溜まりやすい部分を重点的に塗布し“空気と水分を遮断するバリア”を形成します。錆止め層はこの後の上塗り2回を支える大切な下地となり、最終的な耐用年数を大きく左右します。
③ 上塗り1回目
錆止め塗料が完全に乾燥した後、上塗り1回目を塗布します。使用する塗料は、耐候性・耐水性・光沢保持性に優れた樹脂系塗料で、霧除け板金のように紫外線と雨水の影響を直接受ける場所に適しています。この1回目の上塗りは塗膜を形成する“基礎層”となり、色と艶のベースを整える役割があります。
【施工写真:霧除け板金上塗り1回目】

写真では、ローラーや刷毛を使いながら均一に塗布している様子が確認できます。霧除け板金の角度や細い立ち上がり部分は塗りムラが生じやすいため、職人が道具を使い分けて丁寧に塗り進めています。1回目の上塗りは、塗料の食いつきを良くするためにやや薄めに均一に広げ、次に塗る2回目の仕上げ塗装がスムーズに乗るように塗膜を整えます。この工程を丁寧に行うことで、塗り重ねた際の色ムラや艶ムラが起こりにくくなります。
④ 上塗り2回目(仕上げ塗装)
上塗り2回目は、霧除け板金の最終仕上げ工程です。塗膜に必要な厚みを持たせ、耐久性・防水性・光沢を最大限に高める仕上げ層となります。2回塗りによって雨水が弾きやすい膜が形成され、汚れの付着も防ぐ効果が得られます。
【施工写真:霧除け板金上塗り2回目】

写真では、1回目よりもしっかりとした塗膜が乗り、表面が滑らかに整っている様子が見られます。仕上げ塗装は塗膜の厚みを均一に保つため、ゆっくりと丁寧に塗り進める必要があります。とくに端部や折り返し部分に塗料が溜まりすぎないよう注意しながら、均一で美しい光沢を出すよう調整しています。仕上がった霧除け板金は、新品同様の輝きと防水機能を取り戻し、今後の耐久性が大幅に向上しました。
換気フードとは|構造・機能・鉄部としての弱点を徹底解説
換気フードは、室内の湿気や臭気を排出するために設置される金属製の排気口カバーで、台所・洗面所・浴室など水まわりに直結する重要な設備です。外壁に取り付けられ、内部からの排気によって生じる水蒸気や油分、空気の流れなどが直接接触するため、鉄部の中でも特に腐食が早く進む部位として知られています。
換気フードの構造は、金属製のフード本体と外壁取付部、内部の排気ダクトで形成されていますが、このうち外装部である金属部分は常に外気にさらされています。雨風・紫外線・温度変化を受けるだけでなく、内部から排出される湿気や油分が接触することで、一般的な鉄部よりも過酷な環境下に置かれています。このため、塗膜が少しでも劣化すると急速に錆が広がり、塗膜の剥離・腐食・穴あきへと進行するケースが多く見られます。
さらに八王子市中野山王は、冬季は山の冷気が入りやすく、気温差による結露が発生しやすい地域です。換気フードの裏側に水滴がつきやすく、外部の雨水と内部からの湿気の両方が混ざり合うことで、錆の促進環境が整ってしまいます。特に水蒸気が発生しやすいキッチン換気のフードは、油分を含む湿気が付着するため、放置すると錆が一気に拡大することも珍しくありません。
換気フードの施工工程|霧除け板金と同様に“下地処理”が命
① ケレン作業(表面調整)
換気フードの塗装においても、最初に行うのはケレン作業です。表面の錆・汚れ・旧塗膜を削り落とし、鉄部をフラットで清潔な状態に整えます。換気フードは湾曲した部分が多いため、平面の霧除け板金よりも作業難易度が高く、手工具を使い分けながら丁寧に処理を進めます。
【施工写真:換気フードケレン】

今回の写真では、換気フードの曲面に沿ってサンドペーパーを当て、錆や浮いた旧塗膜をしっかり削り取っている様子が確認できます。換気フードは凹凸が多いため、平面部分・カーブ部分・端部に合わせ、粒度の異なる研磨材を使い分けて作業を行いました。油分が付着している場合は研磨前に脱脂作業も行うことで、塗料の密着性を高めます。ケレン後には、鉄部の表面に微細な傷がつき、塗料がしっかりと噛み合う状態(アンカー効果)をつくり、耐久性の高い塗膜形成が可能になります。
② 錆止め塗装
ケレンで整えられた換気フードに対して、エポキシ系の錆止め塗料を塗布します。換気フードは湿気による腐食が非常に早いため、この工程は鉄部の中でも特に重要です。錆止め塗料が金属表面を覆うことで酸素と水の接触を遮断し、腐食を抑制します。
【施工写真:換気フード錆止め】

写真では、換気フード全面に均一に錆止めが塗られている様子が確認できます。錆止めは単に“下塗り”ではなく、鉄部を守るための“防錆層”であり、施工の丁寧さが耐用年数を大きく左右します。特に折り返しや排気口周辺は錆が発生しやすいため、塗り残しがないよう慎重に塗布しました。エポキシ系の錆止め塗料は密着性・防錆性ともに非常に高く、上塗りとの相性も良いため、換気フードのような湿気負荷の大きい部位に最適です。
③ 上塗り1回目
錆止めが完全に乾いたら、上塗りの1回目を塗布します。換気フードは丸みを帯びた形状をしているため、ローラーと刷毛を使い分けることでムラを防ぎながら均一な塗膜をつくります。使用する塗料は、耐候性・耐湿性・耐水性に優れたシリコン系またはラジカル制御型塗料が中心で、鉄部に求められる防水性と耐久性を確保します。
【施工写真:換気フード上塗り1回目】

写真では、職人が曲面に沿って丁寧に塗料を広げている様子が確認できます。換気フードは垂れやムラが発生しやすいため、塗料の量を細かく調整しながら塗り進める必要があります。特に、排出口周辺は空気の流れにより汚れが付着しやすい箇所であるため、塗膜の厚みを均一に保ち、耐久性を確保できるよう注意を払いました。この1回目の上塗りは仕上げ塗装の基礎層となるため、滑らかな膜を形成することが重要です。
④ 上塗り2回目(仕上げ塗装)
最後に上塗り2回目を行い、換気フード全体を仕上げます。2回目の塗装によって塗膜の厚みが十分に確保され、防水性・耐候性・光沢が向上します。雨水のはじきがよくなることで汚れが付着しにくくなり、美観維持にも大きく貢献します。
【施工写真:換気フード上塗り2回目】

写真では、仕上げ塗装によって表面に均一な光沢が生まれ、塗膜の厚みも十分に確保されている様子が確認できます。換気フードは雨水が直接流れ落ちやすい形状のため、耐水性を重視しながら塗膜を構築することが非常に重要です。2回目の塗装では、1回目よりもゆっくりと丁寧に塗り進め、塗料の伸びや光沢が最大限に発揮されるよう技術的な調整を行っています。仕上がった換気フードは、新品同様の見た目と耐久性を取り戻し、今後の腐食リスクが大幅に減少しました。
鉄部塗装に使われる塗料とその材料科学|塗膜の仕組みを理解する
鉄部塗装の品質を左右する大きな要素のひとつが「塗料の材料科学的な性質」です。塗料は表面に色をつけるだけではなく、金属を酸化から守り、腐食を遅らせる“機能材”としての側面を持っています。今回の霧除け板金・換気フード塗装に使用した各層の塗料について、専門的な視点から解説します。
■ 錆止め塗料(エポキシ樹脂系)
錆止め塗料の中でも、エポキシ系は特に密着性・防錆性・耐薬品性が高く、鉄部の長寿命化には欠かせない存在です。エポキシ樹脂は分子結合が強く、塗膜内部に「架橋構造」と呼ばれる強固なネットワークを形成することで、水分や酸素の浸入を大幅に抑えます。
この架橋構造が強固であるほど、塗膜は劣化しにくくなり、鉄部の錆発生を長期的に防ぐことができます。錆止め塗料は鉄部塗装の“土台”となる最も重要な層であり、この層が適切に施工されているかどうかで耐用年数が大きく変わります。
■ 上塗り塗料(シリコン系・ラジカル制御型)
上塗りには、紫外線・雨水・温度変化に強いシリコン樹脂塗料や、近年主流となっているラジカル制御型塗料を使用します。特にラジカル制御型は、紫外線の照射によって発生する“ラジカル”という劣化因子を抑制する働きがあり、従来のシリコンよりも耐候性が高く、鉄部の美観を長期間維持することができます。
鉄部は外壁よりも紫外線を吸収しやすい特性があるため、耐候性能の高い上塗り塗料を使うことは非常に重要です。塗膜が劣化すると小さなひび(クラック)が入り、そこから水が侵入して錆が再発してしまうため、鉄部には強靭で柔軟性のある塗料が適しています。

八王子市中野山王という地域特性が鉄部に与える影響
鉄部塗装の寿命は、使用する塗料や施工技術だけでなく、地域の気候と環境条件によっても大きく左右されます。八王子市中野山王特有の環境要因を整理すると、以下の4つが鉄部劣化の促進要因となります。
① 朝晩の冷え込みが強く「結露」が多い
八王子市は盆地状の地形であり、冬季は特に朝晩の冷え込みが強く、結露が発生しやすい地域です。鉄部表面や裏面に結露水が付着すると、塗膜内部に浸透しやすくなり、酸化を促進します。霧除け板金や換気フードは外気に触れやすく、結露の影響を最も受ける部位です。
② 夏場は強い日差しと高温
中野山王は住宅地でありながら、周囲に日差しを遮る建物が少ない場所も多く、鉄部が直接強い紫外線を受けやすい環境にあります。鉄は熱伝導率が高いため、夏場は表面温度が60〜70℃にも達することがあり、この急激な温度変化が塗膜の膨張収縮を繰り返し、劣化を早めます。
③ 住宅密集地による風通しの悪さ
住宅が密集している地域では、風の流れが滞留しやすく、湿気が逃げにくい傾向があります。湿気が溜まると錆の発生速度が上がり、錆止め塗料が弱った部分から腐食が再発することがあります。換気フードは特に湿気負荷が高いため注意が必要です。
④ 花粉・砂埃・車の排ガスによる汚れ
八王子市は春の花粉が非常に多い地域であり、鉄部に花粉が付着すると、湿気と反応して表面に汚れの膜ができます。この膜が錆発生の促進剤となるため、クリーニングを含めた定期点検が推奨されます。
同じ建物で行った外壁塗装もあわせてご覧ください
今回の霧除け板金・換気フード塗装は、同建物で行った外壁塗装工事に続く付帯部の施工です。外壁と鉄部を同時に施工することで、建物全体の美観が整い、経年劣化の同期化によってメンテナンス計画も立てやすくなります。外壁塗装の詳細は、以下の施工記事で紹介しています。
鉄部塗装は建物保護に不可欠|八王子市でのメンテナンスは専門業者へ
鉄部塗装は、外壁塗装に比べると見落とされがちな工事ですが、建物の耐久性を守るうえで非常に重要な役割を果たしています。今回の霧除け板金と換気フードの施工では、ケレン → 錆止め → 上塗り2回という基本工程を徹底し、地域特性に合わせた材料選定と塗膜構築によって、長寿命で美しい仕上がりを実現しました。
八王子市中野山王をはじめ、結露や湿気が多い地域では鉄部の劣化が特に早いため、早めの点検と定期的なメンテナンスが推奨されます。鉄部のサビや塗膜の剥がれが気になる方は、劣化が進行する前にぜひご相談ください。建物の状態に応じた最適な施工をご提案いたします。